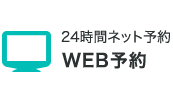2019.01.24 | コラム
マイクロチップがあれば犬の鑑札は不要?意外と間違ってる鑑札との違い。

愛犬にマイクロチップを装着していますか?
マイクロチップは、直径2mm、全長11mmから13mm程度の小さな筒状のチップで、材質に生体適合ガラスを使用しているため、埋め込みにより副作用はほとんど報告されていないと言われています。
最近だと、ペットショップで最初からマイクロチップを装着しているという店舗さんもあり、徐々にマイクロチップを装着しているワンちゃんも増えてきましたね。
それでは、愛犬にマイクロチップを装着済みの飼い主さまに質問です☆
Q:『マイクロチップを装着していれば、愛犬の登録と鑑札の装着は不要になるかどうか?』
A:『マイクロチップを装着していれば、鑑札は不要になる!』
B:『マイクロチップを装着していても、愛犬の登録と鑑札の装着は絶対必要!!』
さあどちらが正解でしょうか☆
マイクロチップも鑑札も『個体識別』するためのものなので、例えば迷子になってしまった時に、飼い主さまがどこの誰なのか?をどちらの方法でも特定することができます。
だからこそマイクロチップと鑑札を混同してしまっている方も多いですよね。
ドッグアシルにご来店されるお客様の中でも『ペットショップの店員さんからは、マイクロチップが装着済みなので、鑑札は不要です!』と言われたという話もよく聞きますし、
ペットショップの店員さんでも、この2つを混同して間違って解釈している方がいる部分ですので、今日は、マイクロチップと鑑札について詳しくお話しようと思います☆
鑑札とマイクロチップの違い
犬の鑑札とは?
まずは、『鑑札』について説明しましょう☆もちろん動物はたくさんいますが、トリミングサロンなので『犬』についてお話します。
『狂犬病予防法』という法律では以下のことが書かれています。
(登録)
第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあって は、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところによ り、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬 の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬につ いては、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に 犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
つまり!!
ペットショップやブリーダーなどからワンちゃんを購入したり、人からワンちゃんを引き取った場合も、『ワンちゃんを飼ったら『30日以内』に所在地の『市町村長』に必ず『愛犬の登録』を申請しなければいけないよ!!』と法律で定められているんですね!
また、愛犬の登録申請を受けた市町村長は、『飼い主の情報』を原簿に登録して、飼い主に『鑑札』を交付しないといけませんよ〜!!
さらに、鑑札をもらった『飼い主』は、その鑑札をタンスの奥にしまってしまうのではなくて、『必ずワンちゃんの首輪など』に常に着けておく責任がありますよ〜!!とも法律で定められているんですよ!
これは、飼い主に対して『協力してください!』という『努力規定』ではなくて、『飼い主の義務ですよ!』ワンちゃんを飼っている以上は、愛犬の『登録申請』と『愛犬に常に鑑札の装着』をする『責任』がありますから必ずやってくださいね!ということです☆
犬のマイクロチップとは?
次にマイクロチップについてご説明しましょう☆
マイクロチップは、『飼い主』が『どこ』の『誰』なのかを明確化することで、例えば、迷子になってしまった時や、震災などの災害が起きた時に、もしもマイクロチップが装着されていれば、そのマイクロチップの情報から飼い主をすぐに特定して、迅速に飼い主の元にワンちゃんを戻すことができるよね!
っということから、『動物の救護活動の円滑化』を目的に、動物愛護団体を中心にマイクロチップの普及がされてきました。
つまり、マイクロチップは、『動物愛護法』で、誰が飼い主なのかを明示するように、何かしらの措置を講じて欲しいので、できればマイクロチップを装着してください!という『努力規定』として定義されています☆
鑑札とマイクロチップのメリット
鑑札
マイクロチップに比べて鑑札は『費用が安い』ことが、マイクロチップがなかなか普及しない理由ですね。
マイクロチップの装着には、だいたい1万円ほど施術料がかかりますが、これも、動物病院によって施術料金は異なってきます。
鑑札はチャームのようなプレートなので、特別な工具等を必要とせず、飼い主が愛犬の首輪などに簡単につけることができます。マイクロチップのように、ワンちゃんの体内に埋め込む必要がないこともメリットでしょう。
また、鑑札は、首輪に着けてあるため、特別な読み取り機等を使わなくても、目視で登録番号から飼い主を容易に特定することが可能です。
例えば、愛犬が脱走して、迷子になってしまった時のことを考えてみましょう☆
迷子犬を保護した人がいた時に、首輪の鑑札は目視で確認できるため、その番号から飼い主を特定し連絡することが容易にできます。
もしもマイクロチップを装着していたとしても、ワンちゃんの体内に埋め込んでいるため、迷子犬を保護した人がいたとしても、鑑札を着けていなければ、目視で確認することができません。
マイクロチップは、専用の『マイクロチップ読み取り機』がなければ『登録番号』を確認することができないため、鑑札の方が、誰がみてもすぐに登録番号が把握できるのは大きなメリットですよね☆
マイクロチップ
マイクロチップの最大のメリットは、『紛失しない!』ということです。
鑑札は、登録番号が書かれているプレートを首輪につけるため、何かの拍子で、首輪から外れてしまったり、経年劣化やワンちゃん自身が噛んでしまって、プレートに書かれている番号が読めないほど破損してしまうということが起こると、登録番号から飼い主の特定をすることができなくなってしまいます。。
それに比べてマイクロチップは、ワンちゃんの体内に装着されているため、シャンプーなどで濡れても、激しく動いたとしても、紛失するリスクが低く、専用の読み取り機があれば飼い主を特定することができます。
昨今でいうと、例えば大きな地震や津波といった震災の時に、首輪自体がワンちゃんから外れてしまったとしても、マイクロチップが装着されて入れば、飼い主の元へ返すことが可能というのが最大のメリットだと思います。
鑑札のデメリット
鑑札のデメリットは、先ほども書いたように、鑑札自体の脱落や経年劣化によって登録番号自体が読めない状況になると、飼い主を特定することができなくなってしまうことです。
マイクロチップのデメリット
マイクロチップのデメリットは、施術料金が一律ではなく、動物病院によって金額が異なる点や比較的高額ということ!
また、体内にマイクロチップを埋め込む行為が可哀想で、飼い主の理解を得難いというのも、なかなか普及しない大きな理由になっていると思います。
さらに、マイクロチップは、目視で確認することができず、『マイクロチップ読み取り機』が必ず必要となるため、その読み取り機の整備やその取り扱い方の周知といった問題点もあります。
鑑札とマイクロチップの答え合わせ
初めに出した問題の答えについて、ここまで読んでくれた方は、もうお分かりですね☆
Q:『マイクロチップを装着していれば、愛犬の登録と鑑札の装着は不要になるかどうか?』
A:『マイクロチップを装着していれば、鑑札は不要になる!』
B:『マイクロチップを装着していても、愛犬の登録と鑑札の装着は絶対必要!!』
鑑札は、『狂犬病予防法』で『狂犬病予防済票』と同じく、『役所への届出』と『首輪等愛犬へ常に装着』が『義務化』されています。
以前のコラムで書いたように、狂犬病予防法は、ワンちゃんの狂犬病感染を守るための法律ではなく、『人を守るため』の法律ですので、狂犬病を打たないといけない動物を誰が飼っているのかを特定と管理をして、飼い主の判断で狂犬病予防接種を打たない!といったことのないようにするために、
『ワンちゃんを飼ったら必ず飼っていることを届出てください!』と飼い主に責任を持たせていますので、マイクロチップを装着しているからといって、届け出ることを免責にするようなことはありません!!
だから☆
答えは『B』ですよ〜☆
マイクロチップを着けているから、『愛犬の登録申請が不要』になったり、『鑑札』を着けなくても良い!ってことはありません☆
首輪には、必ず『鑑札』と『狂犬病接種済票』に装着が『飼い主への義務』となっていますので、もし着けていなかった!!っという方は、ぜひこの機会に、愛犬の首輪に着けていただけたらと思います☆

この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。